こんにちは。EDUCAMP代表の曽雌りょうたです。名古屋を中心に、幼児期から中学生までの子どもたちに、野外教室や探究教室を通じて、社会で生きていくための力を育む教室を運営しています。
子どもたちの姿は、大人の関わり方次第で大きく変わりますよね。多くの子どもたちと向き合う中で、あ~でもない、こ~でもないと、試行錯誤を繰り返す日々をお届けしていきます。
EDUCAMPでは平日の夕方に、子どもたちがテーマをもとに、様々なお仕事を探究する「おしごと探究教室」を実施しています。
目的としては、世の中にある様々な仕事を切り口に、自分の興味や関心を広げ、実践的なアウトプット力を身に着けるというところです。
実際の仕事を切り口にすることで、最終的には成果物が必要になりますので、学んだことが社会の中でどう活用されているのか、というゴールと合わせて学びを進めることができるわけですね。
具体的には、2か月で1つのお仕事を探究していくのですが、探究をするお仕事テーマ自体は事前に決まっています。自分が興味や関心を持ちやすいものは何か、はたまた、そうでないものは何かという視点も含めて、将来のキャリア選択を考える上での原体験になればという考えもあるわけです。
今でこそ全国で広がっている探究学習なわけですが、この教室を始めてかれこれ8年ぐらいになります。
探究学習100【幼児〜中高生対象】探究学習の総合プラットフォームtankyu100.aschool.co.jp
さて、本題に戻りましょう。
子どもをその気にさせるには、きっとこうだろうを外すことから
昨日は、水曜日クラスの2025年の初回授業がありました。低学年中印のエントリークラスは「エレキエンジニア」がテーマです。
簡単に言えば、自分で電子回路を組んで、オリジナルの電子工作を創っていくテーマになります。
エレキエンジニア – なりきりラボ|探究学習100暮らしや仕事につながる探究学習プログラム「なりきりラボ」「おしごと算数」(グッドデザイン賞受賞)を中心としたラインナップ。tankyu100.aschool.co.jp
「さて、今日から始まるのは、エレキエンジニアです」
「え~、理科でやった~」
「もう知ってるし~!」
すかさず、小学3年生の女子sがそう反応してきます。
こういう反応が返ってくると、ついつい嬉しくなっちゃいますよね。
自分たちはもう何でもかんでも素直に喜ぶ子どもじゃないから、生半可なことでは面白がってやらないよ。
女子ーズの心の声(想像)
子どもたちって、あえてこんな風に斜に構えてみて、大人の反応を伺ってくる感じがありますよね。そういう反応がくると、なんともワクワクしてきますよね(笑)
ふふふ、、、。
さあ、その心をどうやって動かしてやろうか、と(笑)
まずはジャブから。満面の笑みで尋ねてみます。
曽雌「お!そうなんだ。流石!じゃあ、今日はエレキエンジニアについてのクイズが結構あるんだけど、全部正解できそうだね」
女子s A 「ええ!?それは、どうかな。だって、ここの授業は学校と違うから」
女子s B 「そうそう!学校じゃ学ばないから、知らないこともあるかもしれない」
ふふふ、、、勝利!
なんともあっけない幕切れでしたね (笑)
もうこの段階で、ほぼほぼ彼女らの集中力を手中におさめたも同然です。
さて、追い打ちにもう一手打ってみましょうか。
「じゃあ、新しい発見があるかもしれないね。さて、今日からやっていくのは、、、電気の仕組みを操れるようになることです!」
「え~!!電気の仕組みを操る?」
「そうそう!つまり、ピカチュウになるってことです」
「いや、そんなわけないじゃん!!」
「まあ、それは冗談なんだけど(笑) 世の中の多くの物は、電気で動いているのは知っているかな?」
「知ってるよ!」
「おお、流石。そして、その電気で動いている物たちの中では、目に見えない電気の通り道ができているんだね。今回、学んでいくと、そんな電気の通り道を自由自在に操れるようになるんだ!」
「おお!」
「でもね。電気って、危ないものでもあるから、一歩間違えると大きな事故に繋がってしまうかもしれないのを知っているかな?」
「知ってる!知ってる!感電しちゃうんでしょ?」
「そう。良く知っているね。使い方を間違えると大きなケガをしちゃうんだ。だから、今日から電気を操るための学びをしていくよ」
さて、お分かりいただけただろうか。
子どもたちの興味のスイッチは、もう完全にONになっていることが。
僕が意識していたのは次の2点
①「え!?」という「きっとこうだろう」を外すこと
②「知ってる!」という「自分の身近なこと」に繋げること
を繰り返していったんです。
その結果、子どもたちの中では、身近なことなんだけど、自分の知らない領域がある!という意識が芽生え、「知りたい!」という欲求が生まれていったんですね。
勿論、一人ひとり興味も関心も性格も違うので、一概には言えませんが、たいていこの繰り返しな気がします。
その上で、大切なのは「テンポ」と「間(ま)」ですね。まあ、この辺はテクニックな気もするので、置いておきましょう。詳しく知りたければ、また聞いてください(笑)
良くある失敗は、子どもに分かりやすく伝えようと思いすぎて、子どもたちのペースに乗ってしまうこと。
パターン①
斜に構えた子に丁寧に伝えようと、言葉に言葉を重ねて説明していった結果「おもしろくな~い」となってしまう
パターン②
無理やり話を聞かせようと「そんなこと言ってないでしっかり聞きなさい!」と抑え込もうとしてしまう
どちらも子どもたちの興味や関心は離れてしまうんですね。
そして、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、これって実は、子どもと大人の関係性の問題でもあるんです。
どちらの失敗パターンも、何を学ぶかではなく、大人が子どもに無理やり学ばせようとする関係性ができてしまったが故の失敗なんです。
そう思うと、子どもたちの姿が、どれだけ大人の姿勢によって変わるかが見えてきますよね。
さて、今日のまとめです。
子どもをその気にさせるには、きっとこうだろうという外すことから。
子どもたちは、大抵の場合、「はいはい、こうすればいいんでしょ」という大人の思惑を読んでいます。
そんなとき、「え?何言っているの?違うよ?」と、別の角度からのボールを投げてみてください。
そうして、子どもたちの「え!?」を上手く引き出せれば、もうこちらのもの。
でも、そのためには、大人の焦りが見えてしまってはいけません。さも、当たり前のことのように「え?何言っているの?」といえる胆力が必要になります。
この辺りは、大人のトレーニングが必要かもしれませんね。
さて、今日はここまで。
参考になれば幸いです。また次回もよろしくお願いします!
★音声配信はコチラ★
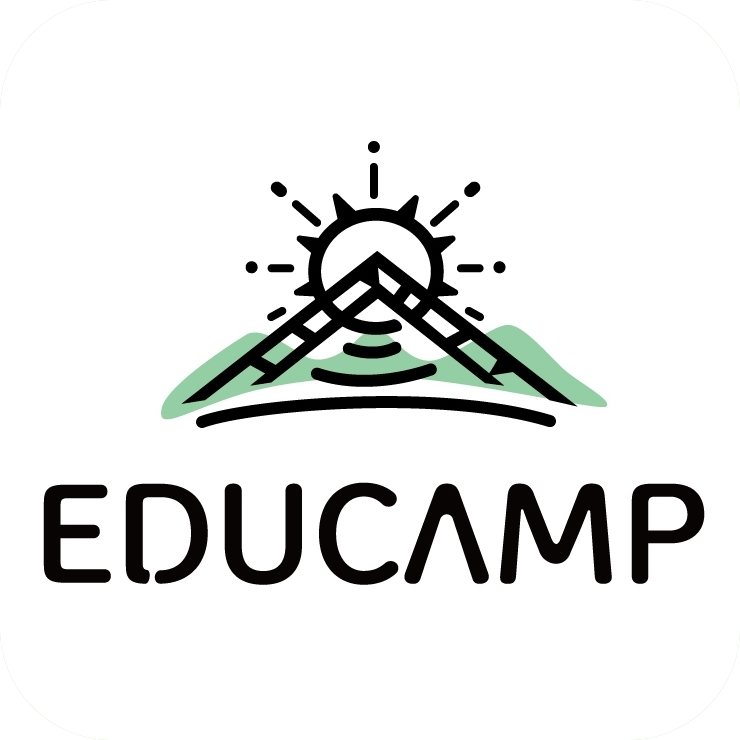 EDUCAMP
EDUCAMP 

